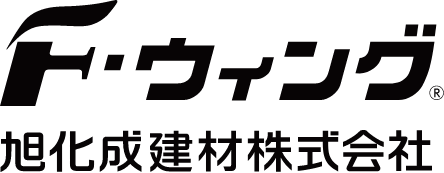Q&A
本Q&Aは、お客様からのお問い合わせの中から特に多いご質問を取り上げています。
本製品をご使用の際は、カタログ等を必ずご一読ください。
また、本Q&Aの記載にご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。
特長
Q1
フリードーナツとのF・ウィング違いは?
A1
-
製品ラインナップの変更
従来のフリ―ドーナツエイトは、φ100~φ400に対応する製品形状はそのままに取付向きを変更し、「F・ウィングエイト」に改称しました。
これに加え、φ100~φ600に対応する新形状のリング「F・ウィングゼット」を新たにラインナップしました。フリードーナツに比べ補強効果の高い「F・ウィングゼット」(片側仕様・両側仕様)により、梁端部などの高い応力が作用する箇所にも貫通孔を設けやすくなりました。
新たな3種類の補強仕様を、梁の応力に応じて選択することで、効果的かつ経済的な補強を可能にできます。 -
部分溶接
F・ウィング工法は、リング外周の梁フランジに平行する2辺以外を隅肉溶接で取り付ける「部分溶接」を採用しました。これにより、溶接トーチが挿入しづらい梁フランジ近傍の溶接が不要でとなり、作業性の向上と溶接量削減が実現されました。F・ウィングエイトでは従来品のフリードーナツエイトに比べ溶接長が25%削減され、在来工法と比較すると、F・ウィングエイトで90%、F・ウィングゼットで80%の削減が可能になりました。 - F・ウィング工法の適用範囲
Q2
F・ウィングを使用するメリットは?
A2
- 在来補強板工法と比べ、貫通孔の大きさや位置など、貫通孔配置の自由度が向上します。
- 在来補強板工法と比べ、溶接量が少なく、貫通孔1箇所あたりの作業時間を短縮できます。
- 溶接量の減少により、溶接による梁の変形、縮みがわずかとなり、矯正等の手間の削減を期待できます。
- 孔径ごとに標準化された製品が、在来補強板工法の補強板寸法の拾い出し作業を軽減するとともに、在庫販売による納期短縮が工期短縮に貢献します。
- 貫通孔部の構造性能を定量的に評価しているため、梁に生じる応力に応じた貫通孔部の安全性の確認が可能です。
- 梁端部の塑性化領域にも貫通孔を設けることができます。(諸条件があります。詳しくはカタログ等をご覧ください。)
Q3
F・ウィングの構造上の安全性は?
A3
-
実大実験やFEM解析の結果に基づき求めたF・ウィングによって補強された貫通孔部の構造的性能は、一般財団法人日本建築センターの評定取得により、その妥当性を確認しています。
評定番号はBCJ評定-ST0265-03です。
Q4
F・ウィングの材質は何ですか?
A4
F・ウィングエイト
建築基準法第37条第二号に基づく国土交通大臣認定を取得したBRリング(SN-BR490B)
認定番号MSTL-0504
F・ウィングゼット
FRリング:SM490YA(JIS G 3106)
Q5
F・ウィングエイトとF・ウィングセットの違いは?
A5
耐力、形状、施工方法にそれぞれ特長がありますが、設計条件も異なるため、ご使用の際は詳細をカタログ等でご確認ください。
Q6
片側補強と両側補強の違いは?
A6
貫通孔に対する補強効果が違うことから、補強後の有孔部梁耐力が異なります。貫通孔部に生じる応力を上回る有孔部の梁耐力となるよう片側補強と両側補強を使い分けます。
- F・ウィングエイトは全サイズで片側補強のみとなります。
- F・ウィングゼットは全サイズで片側補強と両側補強があります。
設計
Q1
F・ウィングを使用する際にどのような検討が必要ですか?
A1
F・ウィングを使用する際は、適用範囲と設置位置条件及び貫通孔位置応力に対する有孔部梁耐力について確認が必要です。これらの検討は、弊社にてサービスで行っていますので、お問い合わせ>ください。
Q2
なぜ有孔部の耐力の検討が必要なのですか?
A2
F・ウィングは、ウェブに開孔を施すことによって低下した梁の耐力を100%元に戻す補強ではありません。
しかしながら、貫通孔位置に生じる応力に対して、妥当性を認められた評価式により求めた有孔部梁耐力が上回ることを確認することによって、安全性を確保します。
Q3
検討を依頼する際に必要な資料はありますか?
A3
以下の資料をCADデータ(dxf/dwg/jww)でご提供ください。
- 伏図・スリーブ図
- 軸組図
- 梁の部材リスト
- 伏図・スリーブ図に関しては、スリーブ高さ位置と径がわかるものをお願いします。
Q4
検討時の貫通孔位置の応力はどのように求めていますか?
A4
弊社にて仮定した![]() 梁応力計算モデルに基づき、貫通孔位置に生じる応力を求めています。
梁応力計算モデルに基づき、貫通孔位置に生じる応力を求めています。
なお、計算条件(長期荷重など)の変更が必要な場合は、弊社までご相談ください。
Q5
梁せいに納まればF・ウィングは使用できますか?
A5
「F・ウィング エイト」「F・ウィング ゼット」ともに梁のフィレットとの干渉を避けての設置する必要があります。
主な梁への取付可能範囲一覧表>をご参照ください。
ただし、貫通孔位置に生じる応力によって、上記を満足しても使用できない場合があります。
Q6
スプライスプレートおよびガセットプレートとはどれくらい離せば良いですか?
A6
「F・ウィング エイト」「F・ウィング ゼット」ともに50mmです。
詳細は取付位置の規定>をご参照ください。
Q7
F・ウィング同士の間隔はどれくらい離せば良いですか?
A7
F・ウィング同士の孔間隔は必要孔間隔一覧表>をご参照ください。また、「F・ウィングエイト」と「F・ウィングゼット」を隣り合わせることも可能です。
Q8
一本の梁内でのリング数制限はありますか?
A8
取付位置の規定>を満足すれば、リング数に制限はありません。
Q9
梁せい方向に複数リング設置は可能ですか?
A9
できません。梁の材軸に対し鉛直方向(せい方向)に複数の貫通孔設置は不可とします。
Q10
SRC造の梁には使えますか?
A10
使用できません。鉄骨造の梁が対象です。
Q11
F・ウィングの内径より小さい孔に使用できますか?
A11
はい。施工手順>に記載の範囲内であれば使用できます。
Q12
垂直ブレースが取り付く梁に使えますか?
A12
梁に軸力が作用する場合は使用不可とします。
施工
Q1
リングに印字はありますか?
A1
製品のリング表面にロット番号、部品記号、必要隅肉溶接サイズを印字>しています。
Q2
連続孔の場合、溶接において配慮することはありますか?
A2
構造評定上の制限はありませんが、片側連続補強によって溶接ひずみが想定される場合は、両面にバランスよく配置されることをお勧めします
Q3
下孔径の許容差はいくつですか?
A3
「F・ウィング エイト」「F・ウィング ゼット」ともに±2mmです。
Q4
リングと梁ウェブの隙間が2mm以上あいてしまったらどう対処したらよいですか?
A4
シャコ万等によりリングと梁ウェブを密着させてください。
ただし、ウェブ側の変形が著しく大きい場合、あらかじめ梁の歪みを適切な処理で取り除いてください。
Q5
F・ウィングはめっき処理できますか?
A5
リングと梁の隙間から錆垂れが発生する可能性がありますので、隙間を無くす必要があります。
「F・ウィング エイト」「F・ウィング ゼット」ともにリング内周で隙間を解消することができないので、めっき処理が必要な梁に使用することができません。
Q6
組立て溶接は必要ですか?
A6
組立て溶接は、梁フランジに平行する2辺以外に等間隔に2~4箇所、リングの左右で対称となるような箇所に行ってください。1箇所の長さは40mm以上、1パスとし、ショートビードにならないように注意してください。また、BRリングは外周角部を避け、頂点~頂点の中央付近に組立て溶接を行ってください。
Q7
F・ウィングの設置方向はありますか?
A7
「F・ウィング エイト」「F・ウィング ゼット」ともにリング直線部が梁フランジと概ね平行になるように設置してください。
Q8
下孔径は呼び径と同じですか?
A8
「F・ウイングエイト」「F・ウィングゼット」とも下孔径は呼び径と同じです。また、下表の範囲内で小さくすることが可能です。


※下孔径は( )に記載の範囲で小さくすることができます。
Q9
F・ウィングの溶接の検査はどのようにすればいいですか?
A9
「F・ウイングエイト」「F・ウィングゼット」とも隅肉溶接なので基本的に目視による外観検査が求められます。
Q10
F・ウィングへの耐火被覆はどのようにすればいいですか?
A10
F・ウィング自体には耐火性能はありません。耐火構造の梁でF・ウィングで補強された貫通孔は、その梁ウェブと同様の耐火被覆が必要となります。
なお、開孔部内側の耐火被覆に既製品を使用する場合は、各耐火被覆材メーカーにお問い合わせください。
Q11
向きを間違えて取り付けてしまったらどう対処すればよいか?
A11
現場協議によりますが、基本的にはつけ直しをお願いします。
Q12
F・ウィングは建設現場にて取付可能ですか?
A12
F・ウィングの溶接は工場作業を想定し、梁ウェブ面を上に向けた水平(下向き)隅肉溶接です。建設現場での施工はお控えください。